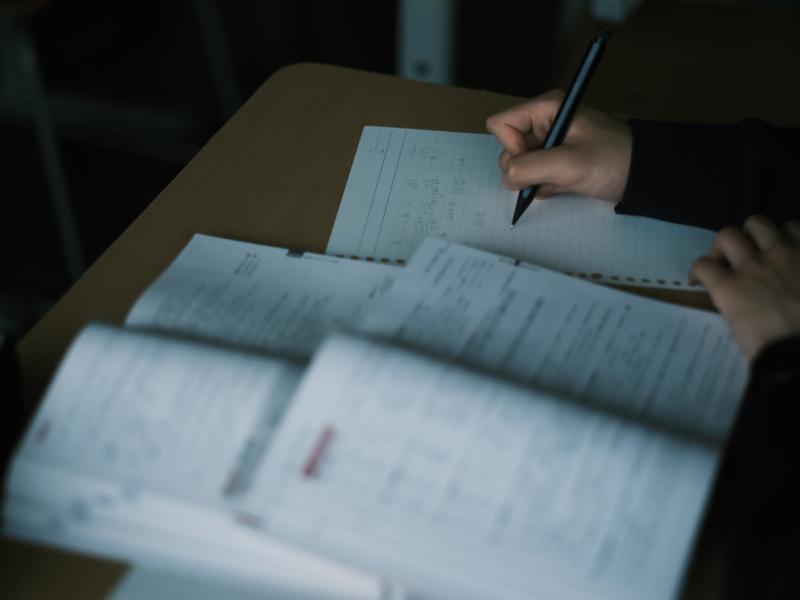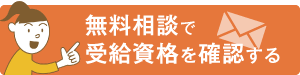障害年金の審査請求後の流れはどうなっているか
障害年金の審査請求後の流れはどうなっているか
掲載日:2025.10.08
障害年金請求をして、その結果が望んだものでなかった場合には審査請求という手続きを取ることになります。
(審査請求までの流れについては上記リンクをご参照ください)
地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行うと、その後の流れがどうなっているかはあまり語られません。
水面下にある状況について少しまとめてみます。
審査請求を行ったあとの流れ
社会保険審査官は社会保険審査官及び社会保険審査会法に規定され設置されており、同法施行規則によると定数は102人とされています。
郵送で審査請求を行うと、まずは受付された旨の通知があります。こちらは数日のうちに書面で返送があります。
その後審査期間に入ることとなりますが、口頭意見陳述を行うかどうかの意向確認があります。
口頭意見陳述は、実際に社会保険審査官と対面し、保険者はオンラインで出席して行われます。文字通り、口頭で意見を述べる機会になります。
行ったから有利になるかと言われると、正直かなり微妙ではあります。経験として、また社会保険審査官と対面する機会はほとんどないので、その意味でアリかもしれません。
口頭意見陳述の開催を希望しなかった場合には開かれず、双方の書面による意見を検討して、社会保険審査官が決定を行います。
審査請求を受け付けた社会保険審査官は、同法第九条に基づき、保険者(厚生労働大臣)、あればその他利害関係者に対して書面で通知をします。
その通知を受け、保険者は保険者意見として、社会保険審査官に対し、処分に至った規定や根拠を示した意見書を提出します。
この意見書については、現在は障害年金センターから、審査請求を行っておよそ2か月程度で提出されているようです。
もちろん長いものも短いものもあるかと思いますし、混雑の度合いでも変わってくるかと思います。
ですので、審査請求を受けて保険者が処分を変更する(請求人の主張を全部または一部認める)場合は、この頃に電話などで連絡が来ることが多いかと思います。
その際には処分変更を受け入れて審査請求の取り下げをするか、仮に申し立てた内容に対してまだ不服があれば、そのまま続行することも可能です。
連絡がない場合(決定が変更されない場合)は社会保険審査官の決定を待つことになります。
社会保険審査官は保険者の意見を受けてから審査請求を容認するか、棄却するかを決定するので、処分変更される場合よりも審査期間は長くなります。
この時に提出される保険者の意見書は、審査請求が棄却後に再審査請求を行い、公開審理前に送られてくる、いわゆる「事件プリント」に掲載されています。
これ以外には「不支給決定通知書」に添付されている不支給・却下の理由、もしくは年金事務所を経由して年金機構本部に問い合わせてもらい、その時に確認できる内容以上のことはわからないこととなります。
不支給の理由にもよりますが、「認定医の判断としか言えない」と言われることも多くあります。
ただし、社会保険審査官は保険者の意見を見ていますし、棄却の決定書に書かれていることが保険者意見そのまま、ということも多く、そこから保険者の意見や不支給の理由となったポイントを読み取ることはできるかと思います。
また、社会保険審査官は、医師や医療機関に対して直接意見を求めることもあります。これは請求者や代理人である社会保険労務士へ連絡なく書面で行うことが多く、医師から聞いたり、決定書を見て知るということもあります。
その内容については当然、決定書に反映されることになりますが、こちらについても「事件プリント」に写しが載ることで見ることができます。
審査請求の結果について
審査請求の結果は、取り下げをしない限りは、「決定書」として、同法第十五条2に基づき、地方厚生局社会保険審査官から書面で送付されます。
更に結果に不服がある場合は再審査請求を行うことになります。障害年金に関する決定はここまでを経ないと訴訟を提起することはできません。
上記のように、審査請求の決定までは長くかかるものもあれば短いものもあります。
保険者の意見提出が遅れたり、医療機関への問い合わせを行っていれば、その分の時間がどうしてもかかってくることになります。
この記事がお役に立ったらシェアお願いします。